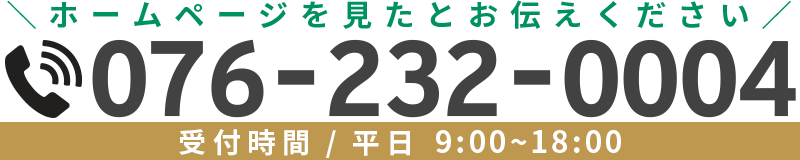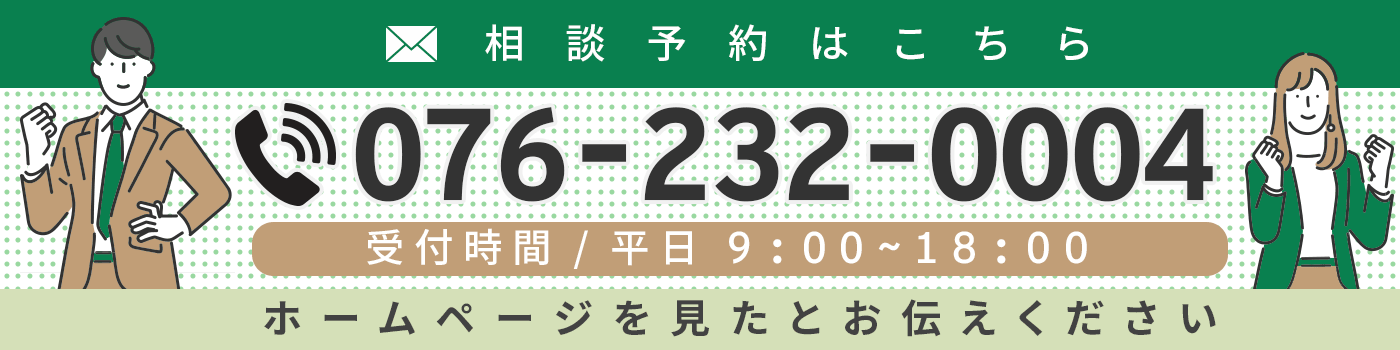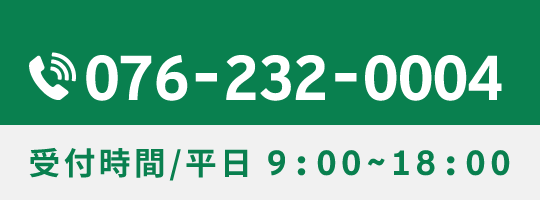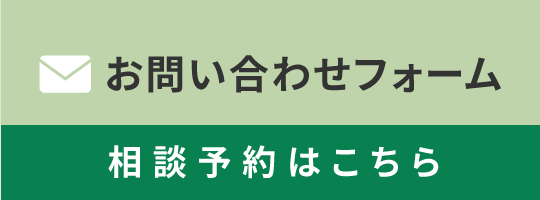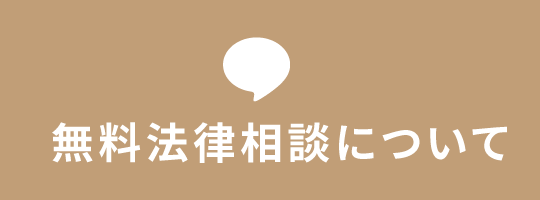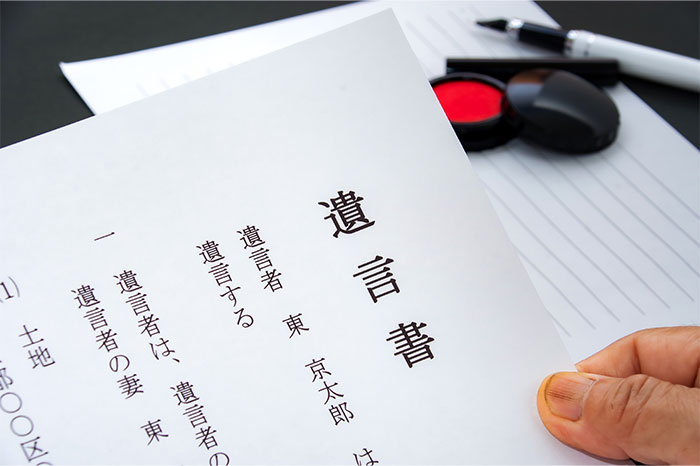
遺言書の作成は、相続トラブルを防ぎ、自分の意思を確実に伝えるための最善の生前対策の一つです。遺言書があることで、相続人間の無用な争いを避け、円滑な相続手続きが実現します。
以下では、遺言書作成のメリットや種類、作成手続きについて詳しく解説します。
このページの目次
1. 遺言書作成のメリット
(1) 相続トラブルの防止
- 遺言書がない場合、遺産分割協議が必要となり、相続人間で意見が対立することがあります。遺言書があると、遺産分配が明確になり、紛争を防ぐことができます。
(2) 特定の相続人への配慮が可能
- 法定相続分にとらわれず、自分の意思で財産を分配できます。例えば、親の介護を担当した子どもに多めに遺産を渡すことも可能です。
(3) 遺留分トラブルの軽減
- 遺言書により、遺留分侵害に配慮した内容を記載することで、遺留分請求による争いを最小限に抑えられます。
(4) 非相続人への遺贈
- 親族以外(例:友人や慈善団体)にも財産を遺すことができます。
2. 遺言書の種類
遺言書には主に以下の3種類があり、それぞれ特徴があります。
(1) 自筆証書遺言
| 特徴 | 遺言者が自分で全文を手書きし、署名・押印する形式。 |
| メリット | 手軽に作成可能。 費用がほとんどかからない。 |
| デメリット | 不備があることに気が付かず、遺言が無効になる可能性が高い。 相続開始後に家庭裁判所での検認が必要。 |
(2) 公正証書遺言
| 特徴 | 公証役場で公証人が作成する遺言書。 |
| メリット | 法的に確実で、無効になるリスクが低い。 原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。 |
| デメリット | 公証人手数料がかかる。 作成時に証人が2名必要。 |
(3) 秘密証書遺言
| 特徴 | 内容を秘密にしたまま、公証役場で証明を受ける形式。 |
| メリット | 内容を秘密にできる。 |
| デメリット | 自筆証書遺言と同様に形式不備で無効となる可能性がある。 |
3. 遺言書作成の手順
ステップ1: 財産のリストアップ
遺産の対象となる財産を全て把握します。
- プラスの財産: 不動産、預貯金、株式、保険など
- マイナスの財産: 借金、ローン、税金など

ステップ2: 相続人の確認
- 被相続人の戸籍を調査し、法定相続人を確定します。
- 代襲相続が発生する場合にも注意が必要です。

ステップ3: 遺産分配の内容を決定
- 相続人や遺贈先にどの財産をどのように分けるかを明確に記載します。
- 遺留分を侵害しないよう配慮します。

ステップ4: 遺言書の作成
- 自筆証書遺言: 遺言書を全文手書きで記載し、署名・押印します。
- 公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらいます。証人が2名必要です。

ステップ5: 保管
- 自筆証書遺言は、遺言者自身で保管するか、法務局の「遺言書保管制度」を利用します。
- 公正証書遺言は、公証役場に原本が保管されます。
4. 注意点
(1) 遺言書の内容が不明確
- 曖昧な表現や誤記があると、相続人間で争いが生じる原因になります。正確で詳細な記載が必要です。
(2) 遺留分への配慮
- 法定相続人には遺留分が保証されています。遺留分を無視した内容の場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
(3) 最新の状況を反映
- 遺言書は、財産や家族構成が変わった場合に更新することが必要です。
5. 当事務所が提供するサポート内容
遺言書作成をスムーズに進めるために、当事務所では以下のサポートを提供しています。
- 財産調査: 遺産の全容を正確に把握し、遺言書に反映します。
- 相続人の確認: 戸籍調査を行い、相続人を確定します。
- 遺言内容の作成サポート: 法律に則った分配内容を提案します。
- 公正証書遺言の作成支援: 公証役場での手続きの代理・同行を行います。
- 遺言執行者の指定: 遺言の内容を確実に実現するため、遺言執行者として対応します。
6. 遺言書作成の費用目安
公正証書遺言
- 公証人手数料: 数万円〜(遺産の総額によって異なります)
- 弁護士費用: 30万円〜(内容や財産の複雑さによります)
自筆証書遺言
- 基本的に費用はかかりませんが、法務局の保管制度を利用する場合は数千円の手数料が必要です。
7. まずはご相談ください
遺言書作成は、相続トラブルを防ぎ、家族への想いを確実に形にする大切な手続きです。「どのように書けばよいかわからない」「複雑な財産がある」などのお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専門家があなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な遺言書作成をサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。