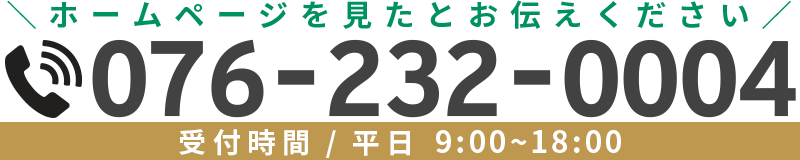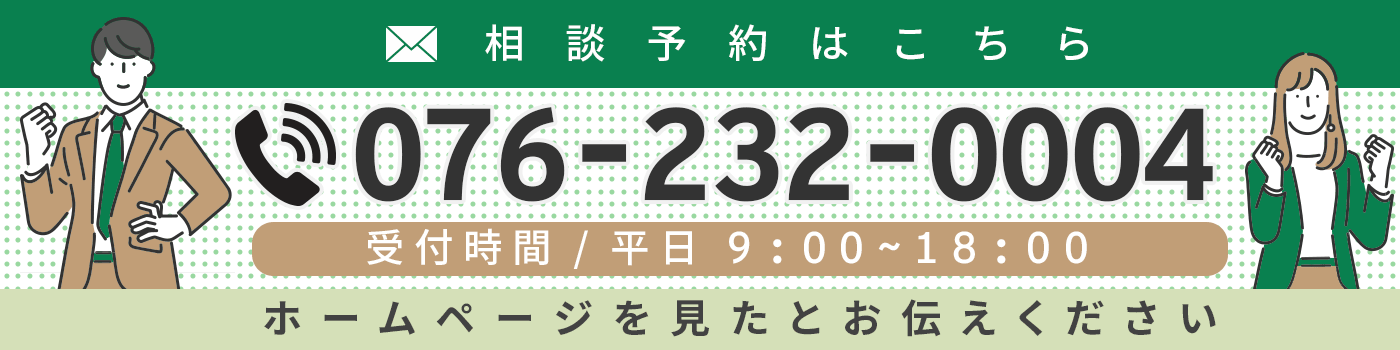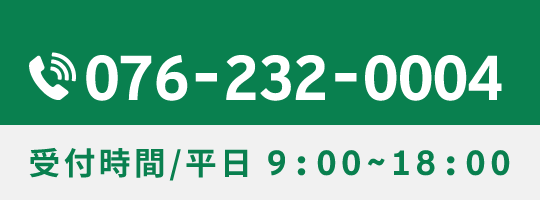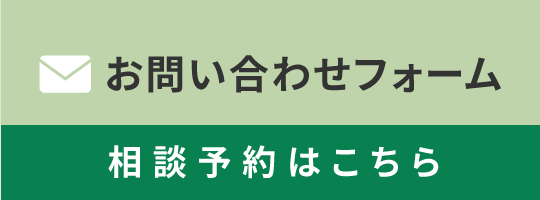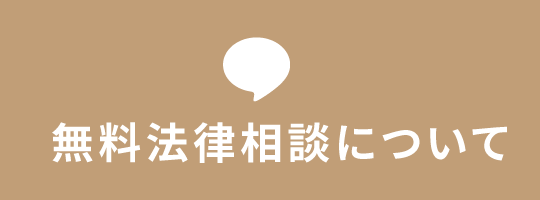遺言書がない場合、法律に基づいて相続手続きを進める必要があります。この場合、相続人全員で遺産の分配方法を話し合い、合意を得る「遺産分割協議」が重要なステップとなります。
遺産分割を巡って意見が対立することもあるため、冷静で適切な対応が求められます。
以下に、遺言書がない場合の一般的な相続手続きの流れを解説します。
このページの目次
1. 相続人と相続財産の確認
まず、誰が相続人となるのか、そしてどの財産が相続の対象になるのかを確定します。
相続人の確定
相続人は民法で定められており、以下の優先順位で確定します。
- 第1順位: 子ども(養子を含む)
- 第2順位: 直系尊属(両親や祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、上記の順位に応じて法定相続分が決まります。
相続人を確定するために必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
相続財産の調査
財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、有価証券など)と、マイナスの財産(借金、ローンなど)が含まれます。
財産を把握することが、適切な分割の第一歩です。
必要書類
- 預貯金通帳や取引明細
- 不動産の登記簿謄本
- 借金の契約書や請求書

2. 相続放棄や限定承認の検討
相続財産に負債が多い場合、相続を受けるかどうか慎重に判断する必要があります。
選択肢
- 相続放棄: 相続人としての地位を放棄し、財産も負債も引き継がない。
- 限定承認: プラスの財産の範囲内で負債を返済する。
これらの手続きは、相続開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所に申立てる必要があります。
当事務所では、これらの判断や手続きをサポートしています。

3. 遺産分割協議
遺言書がない場合、遺産をどのように分配するか、相続人全員で話し合います。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。
協議の進め方
- 遺産の種類と価値を確認する
不動産や金融資産の評価額を明確にし、公平な分配を目指します。 - 相続人全員の同意を得る
協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書に記載する内容
- 相続人の氏名
- 分割対象となる財産の詳細
- 分割方法
協議書に不備があると、後の名義変更手続きが進められないため、慎重に作成する必要があります。

4. 財産ごとの名義変更手続き
遺産分割協議がまとまったら、各財産の名義変更や引き渡し手続きを行います。
不動産
| 必要書類 | 遺産分割協議書、不動産登記簿謄本、相続人の戸籍謄本など |
| 手続き先 | 法務局 |
預貯金
| 必要書類 | 遺産分割協議書、金融機関指定の書類、相続人の本人確認書類 |
| 手続き先 | 各金融機関 |
株式・有価証券
| 必要書類 | 遺産分割協議書、証券会社の指定書類 |
| 手続き先 | 証券会社 |

5. 相続税の申告と納付
遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
申告期限は 相続開始から10か月以内 です。
相続税の計算例:
- 基礎控除額: 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
- 控除額を超える部分に税率を適用
相続税申告は、分割協議の内容によって計算が変わるため、早めの準備が重要です。
当事務所では、税理士と連携し、申告をサポートいたします。

6. 相続手続き完了
すべての名義変更や税務手続きが終われば、相続手続きは完了となります。
書類の保管や家庭内での記録をしっかり残すことも大切です。
トラブルのリスク: 話し合いが難航する場合、調停や審判に進むことがある。
感情的な対立: 親族間の不信感を避けるため、専門家が介入することで冷静な対応が可能。
法定相続分の理解: 各相続人の権利を正確に把握し、不公平感を防ぐ。
当事務所のサポート内容
遺言書がない相続の場合、手続きが複雑化しやすいため、専門家のサポートが役立ちます。当事務所では、以下のサービスを提供しています。
- 相続財産調査
- 相続人の確定
- 遺産分割協議書の作成サポート
- 名義変更や相続税申告の手続き代行
- 調停・審判手続きへの対応
「遺言書がないために手続きが複雑」「親族間での話し合いに不安がある」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
迅速で的確な対応により、安心して手続きを進めていただけるよう全力でサポートいたします。