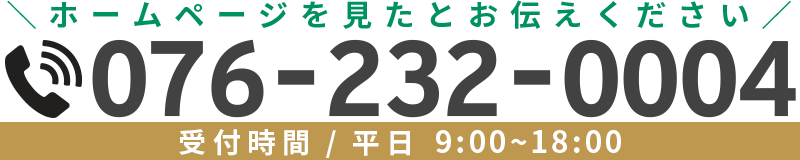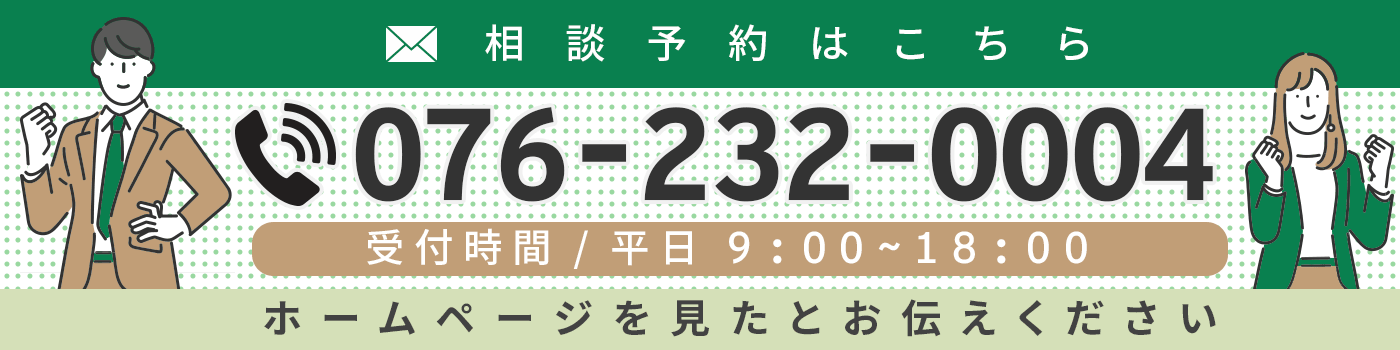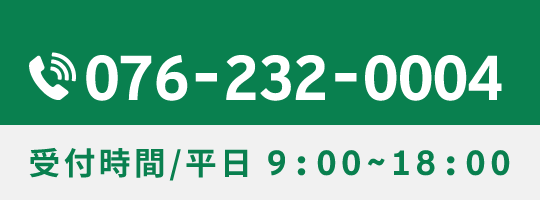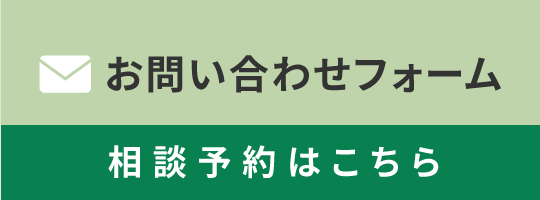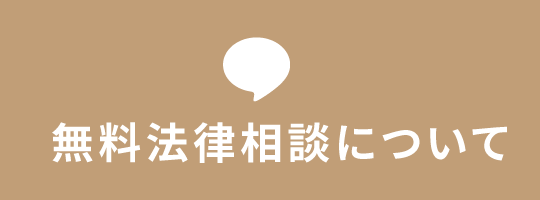2024年4月1日から、相続登記が義務化されることが法律で定められました。
この改正により、土地や建物などの不動産を相続した場合、一定期間内にその登記を行わないと過料(罰金)が科される可能性があります。
この制度は、不動産の所有者不明問題を解消し、円滑な土地利用を促進するために導入されました。法務局から登記をするようにという通知を受け取って、驚いている方もいらっしゃるかもしれません。
法務局も調査をしており、相続人が判明したものについて登記をするように通知をしています。
以下では、相続登記の義務化の概要や手続き方法、注意点について詳しく解説します。
このページの目次
1. 相続登記の義務化とは
義務化の背景
日本では、不動産を相続しても登記をしないまま放置されるケースが増えています。その結果、所有者が分からない土地が増加し、土地の有効利用や公共事業に支障をきたしています。
こうした問題を解決するため、相続登記を義務化する法改正が行われました。
2. 相続登記の義務化の内容
登記義務の期限
相続登記は、以下のいずれかの事実を知った日から3年以内に完了する必要があります。
- 相続が開始したことを知った日(被相続人が亡くなった日)
- 遺産分割協議が成立した日
対象となる不動産
- 土地、建物など全ての不動産が対象となります。
- 農地や宅地、マンションの専有部分も含まれます。
3. 相続登記をしない場合の罰則
義務化に伴い、相続登記を怠ると罰則が科される可能性があります。
- 過料(行政罰): 正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
- 注意: 刑事罰ではなく、行政上の措置として課されるものです。
4. 相続登記の手続き方法
手続きの流れ
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。
複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の同意を得ます。
対象となる不動産を確認し、登記簿謄本や固定資産評価証明書を取得します。
必要書類を揃え、法務局に登記申請を行います。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 固定資産評価証明書(税務署または市区町村役場で取得)
- 相続登記申請書(法務局指定の書式に記入)
5. 相続登記義務化における特例措置
義務化に伴い、次のような特例措置が設けられています。
(1) 簡易な手続きによる相続登記
相続人全員の合意が難しい場合でも、「所有権の申告」のみで暫定的に登記を行うことが認められています。
- 申告内容: 相続人のうち1人が「自身が相続人であること」を申告すればよい。
- 目的: 手続きの簡略化を図り、義務を履行しやすくするため。
(2) 共有状態の解消を促進
複数人で不動産を共有する場合、共有状態の解消を容易にする制度が設けられました。
例えば、単独相続人への持分移転を促す仕組みがあります。
6. 相続登記義務化における注意点
1. 遺産分割協議の遅れ
遺産分割協議が長引くと登記期限に間に合わないリスクがあります。早期に協議を開始することが重要です。
2. 相続人間のトラブル
相続人が複数いる場合、財産分割を巡って意見が対立することがあります。専門家の仲介が有効です。
3. 固定資産税の課税
相続登記を完了すると、固定資産税の課税が開始されます。相続人間で税負担の分担を話し合うことが必要です。
7. 当事務所が提供するサポート内容
相続登記義務化に伴う手続きの複雑さを軽減するため、当事務所では以下のサポートを提供しています。
- 戸籍収集の代行: 被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍収集を代行します。
- 遺産分割協議書の作成: 相続人全員が納得できる内容での協議書作成をサポートします。
- 相続登記の代理申請: 必要書類の準備から法務局での申請手続きまで一括して対応します。
- トラブルの防止: 相続人間の意見調整や紛争解決を弁護士がサポートします。
8. まとめ
相続登記の義務化は、相続人にとって新たな負担となる一方、不動産の所有権を明確にする大切な手続きです。早めに相続手続きを進めることで、罰則を回避し、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
「何から手を付ければよいかわからない」「手続きが煩雑で不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専門家が一からサポートし、安心して相続登記を完了できるようお手伝いいたします。