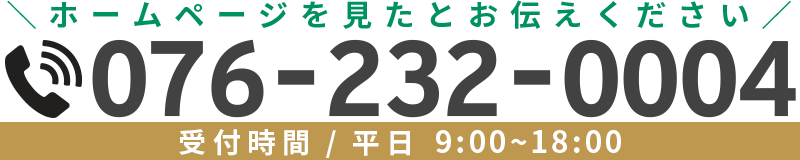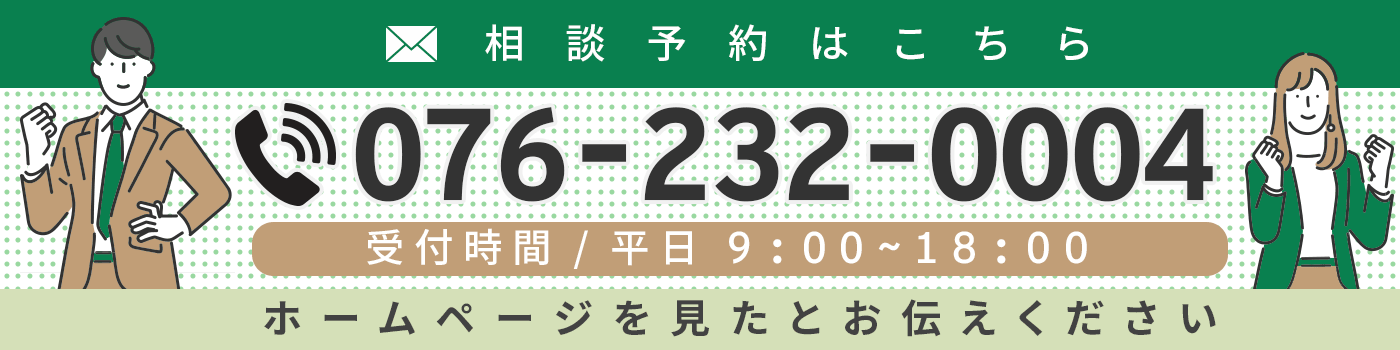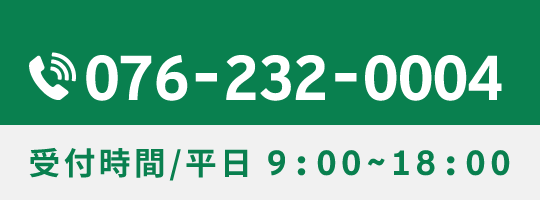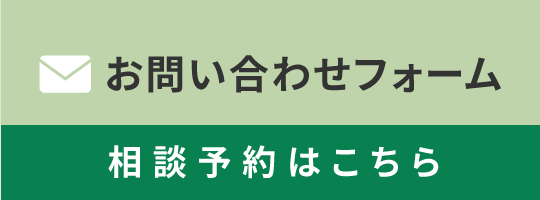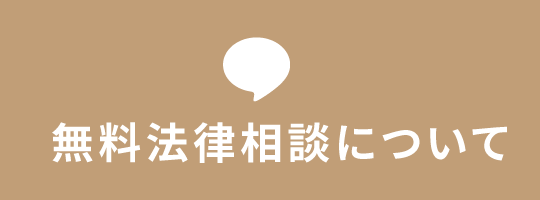被相続人(亡くなった方)が生命保険に加入していた場合、保険契約に基づいて受取人が死亡保険金を受け取ることができます。
生命保険金は、他の相続財産とは異なる取り扱いがされるため、手続きの流れや必要書類、注意点を正しく理解して進めることが大切です。
このページの目次
1. 死亡保険金の基本的な仕組み
生命保険金の特徴
- 受取人に直接支払われる財産
死亡保険金は、相続財産ではなく、受取人固有の財産とみなされます。そのため、遺産分割協議の対象にはなりません。
ただし、相続財産額の多くが保険でありるような場合には、遺産として扱われる場合もあるので注意が必要になります。 - 非課税枠がある
一定の金額まで相続税がかからない仕組みがあります。
非課税枠
相続税の課税対象になる場合でも、以下の金額まで非課税となります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
2. 死亡保険金の受け取り手続きの流れ
ステップ1: 加入保険の確認
被相続人が契約していた生命保険の詳細を確認します。
確認方法
- 保険証券(契約書)の内容を確認
- 保険会社から届く案内や請求書を探す
- 不明な場合は、被相続人の銀行口座の引き落とし履歴を確認

ステップ2: 保険会社への連絡
保険会社に被相続人が亡くなったことを伝え、死亡保険金の請求手続きについて問い合わせます。
連絡時のポイント
- 保険契約者(被相続人)の名前と契約番号を伝える
- 必要書類や手続きの詳細を確認

ステップ3: 必要書類の準備
死亡保険金を請求するために、次のような書類が必要です。
必要書類(一般的な例)
- 死亡保険金請求書: 保険会社が指定する書類(受取人が記入)
- 被相続人の死亡診断書または死体検案書: 原本が必要
- 受取人の本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど
- 保険証券: 契約内容が記載された書類
- 住民票や戸籍謄本:
・被相続人の戸籍謄本(死亡が記載されているもの)
・受取人の住民票または戸籍謄本
その他の必要書類
保険会社によって追加書類が必要となる場合があります。事前に保険会社に確認しておきましょう。

ステップ4: 書類の提出
準備した書類を保険会社に提出します。提出方法は以下のいずれかになります。
- 保険会社の窓口に直接提出
- 郵送で提出
- 指定されたオンラインサービスを利用(保険会社による)

ステップ5: 保険金の受け取り
書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で指定した口座に保険金が振り込まれます。
3. 死亡保険金の相続税に関する注意点
課税の有無
- 非課税限度額を超える場合:
非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を超えた部分に対して相続税が課税されます。 - 課税対象外の場合:
受取人が被保険者(亡くなった方)とは別の法人や団体の場合、相続税ではなく所得税や贈与税が課税される可能性があります。
例外的なケース
- 保険金の受取人が被相続人自身だった場合、保険金は相続財産となり、相続税の課税対象となります。
4. 受取人が未指定または死亡している場合
受取人が保険契約で指定されていない、または受取人がすでに死亡している場合、死亡保険金は相続財産として扱われ、遺産分割協議の対象になります。
この場合、相続人全員で分割方法を協議し、合意を得る必要があります。
5. 手続きの注意点
1. 書類の不備に注意
書類に不備があると手続きが遅れるため、事前に保険会社に必要書類を確認し、正確に記入しましょう。
2. 保険会社ごとに異なる手続き
保険会社によって必要書類や手続きが異なるため、複数の生命保険に加入している場合は、それぞれの会社で確認が必要です。
3. トラブルの回避
受取人が複数いる場合や遺産分割に関連する問題が発生した場合、法律の専門家に相談することをおすすめします。
6. 当事務所のサポート内容
当事務所では、死亡保険金の受け取り手続きをスムーズに進めるため、以下のサポートを提供しています。
- 保険契約内容の確認: 被相続人が加入していた保険の特定をサポートします。
- 必要書類の準備: 戸籍謄本や住民票の取得を代行します。
- 保険会社とのやり取り: 手続きの進捗管理や書類作成のサポートを行います。
- 税務アドバイス: 死亡保険金に関する相続税の計算や非課税枠の適用方法を専門家がご案内します。
7. まずはご相談ください
死亡保険金の手続きは、特に初めての方にとって分かりにくい部分が多い手続きです。当事務所では、初回相談で必要な手続きや注意点について丁寧にご説明します。
安心して手続きを進められるよう、専門家が全力でサポートいたします。
お気軽にお問い合わせください。