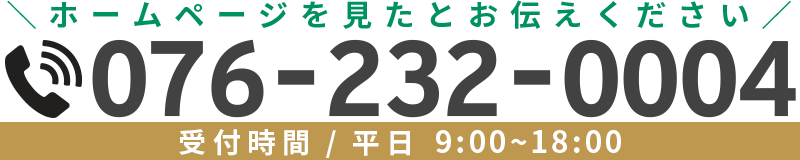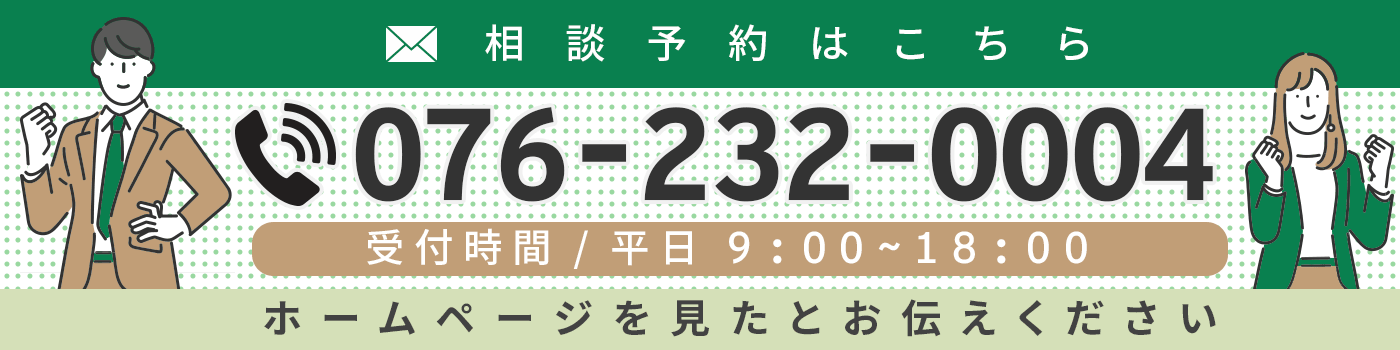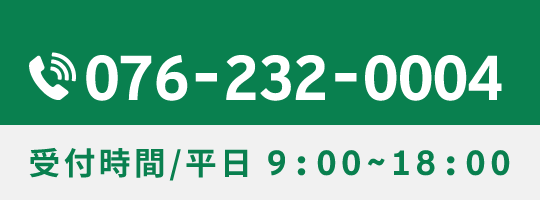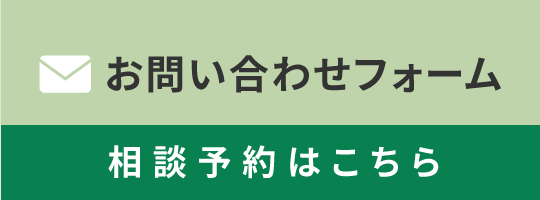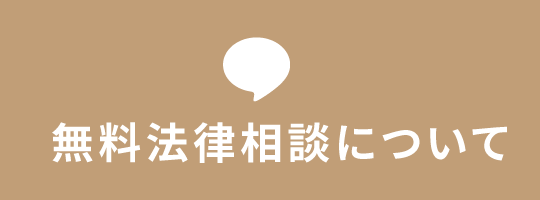遺産分割協議は、相続人全員で話し合い、遺産の分配方法を決定する手続きです。
円満に話し合いが進めば協議書を作成して完了しますが、意見の対立や感情的な問題が絡むと話し合いが難航することがあります。
その場合、家庭裁判所の調停や審判による解決が必要になることもあります。
ここでは、遺産分割協議の流れや調停手続き、注意点について解説します。
このページの目次
1. 遺産分割協議とは
遺産分割協議は、遺言書がない場合や、遺言書に明記されていない財産について、相続人全員で分配方法を話し合う手続きです。
協議が必要な理由
- 公平な分配: 相続財産を法定相続分に基づいて分けるだけでなく、各相続人の希望や家庭の事情を考慮します。
- 全員の同意が必要: 相続人全員が同意しなければ遺産分割協議は成立しません。
2. 遺産分割協議の流れ
ステップ1: 相続人の確定
まず、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。

ステップ2: 財産の確定
相続財産をすべてリストアップします。
- プラスの財産: 不動産、預貯金、株式、保険金など
- マイナスの財産: 借金、ローン、未払いの税金など

ステップ3: 話し合いによる分配の決定
相続人全員で集まり、財産の分け方を話し合います。
分配方法の例
- 現物分割: 財産そのものを分ける
- 換価分割: 財産を売却し、その代金を分ける
- 代償分割: 一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に現金などで補償する

ステップ4: 遺産分割協議書の作成
話し合いで分配方法が決定したら、「遺産分割協議書」を作成します。
- 相続人全員の署名と実印が必要です。
- 協議書は、名義変更手続きや相続税申告の際に使用します。
3. 遺産分割協議がまとまらない場合
話し合いが決裂する理由
- 分配割合への不満: 法定相続分と異なる分割案に対する反対意見
- 感情的な対立: 家族間の不信感や過去の問題が影響
- 財産の評価が難しい: 不動産や骨董品など、評価が複雑な財産
こうした場合、家庭裁判所での「遺産分割調停」に進むことが一般的です。
4. 遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所で中立的な調停委員が仲介し、話し合いを進める手続きです。
調停の流れ
相続人の1人または複数人が家庭裁判所に調停を申し立てます。
必要書類: 相続人関係図、財産目録、被相続人の戸籍謄本など
家庭裁判所から調停期日が指定されます。
調停委員が中立的な立場で相続人間の意見を調整します。
相続人が直接顔を合わせる必要はなく、個別に意見を伝えることも可能です。
調停で分割内容がまとまれば、調停調書が作成されます。
調停調書は、裁判所の決定と同じ効力を持ちます。
5. 調停が不成立の場合
調停でも合意が得られない場合、家庭裁判所が遺産分割を決定する「審判」に移行します。
審判の特徴
- 裁判所が分割を決定: 相続人の意見を聞きながら、法定相続分や相続人の状況を考慮して分割方法を決定します。
- 最終的な解決: 審判の内容に不服がある場合、一定期間内に高等裁判所に抗告することができます。
6. 遺産分割協議・調停の注意点
(1) 相続人全員の参加が必要
遺産分割協議や調停には、全ての相続人が参加する必要があります。
1人でも欠けると手続きが無効となるため、相続人を正確に確定することが重要です。
(2) 感情的な対立を避ける
家族間のトラブルを避けるため、第三者(弁護士や調停委員)のサポートを受けることが効果的です。
(3) 財産評価の透明性
不動産や株式など、評価が難しい財産については、不動産鑑定士や税理士の意見を取り入れると公平な分割が進めやすくなります。
7. 当事務所が提供するサポート内容
遺産分割協議や調停をスムーズに進めるため、当事務所では以下のサポートを提供しています。
- 相続人の確定: 必要な戸籍収集や相続関係説明図の作成を代行します。
- 財産の調査: 不動産や金融資産の調査・評価をサポートします。
- 遺産分割協議書の作成: 法的に有効な協議書を作成します。
- 調停の代理: 調停や審判の場で相続人の代理人として適切な主張を行います。
- トラブル解決: 感情的な対立や複雑な財産問題の解決に向けた調整を行います。
8. まとめ
遺産分割協議や調停は、相続人全員が納得する形で遺産を分配するために欠かせないプロセスです。しかし、話し合いが難航したり、調停に進んだりするケースも多くあります。
「遺産分割協議をどう進めればいいかわからない」「調停が必要になったが不安」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専門家があなたの立場に立って適切な解決をサポートします。