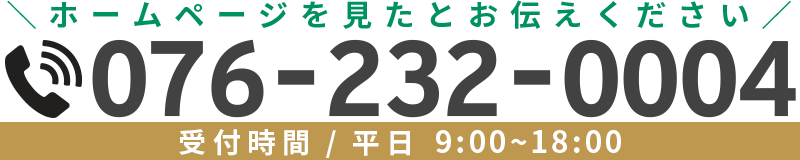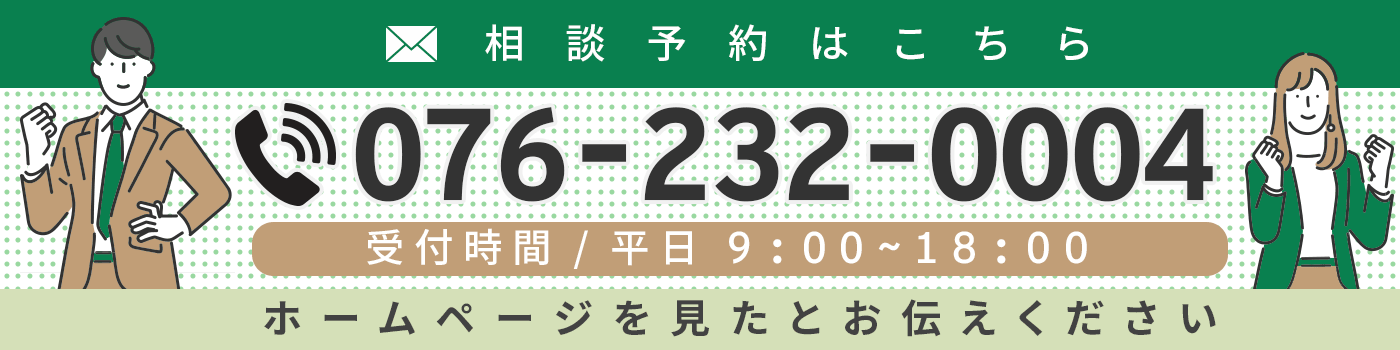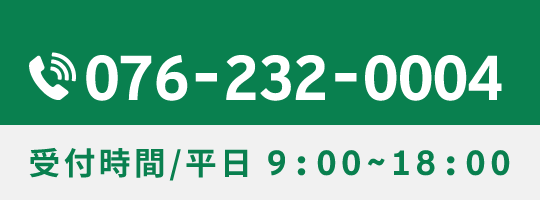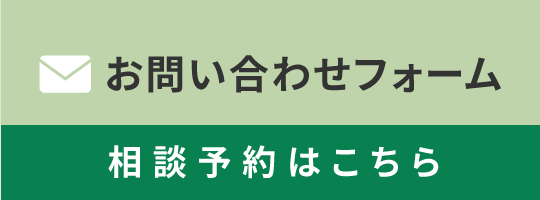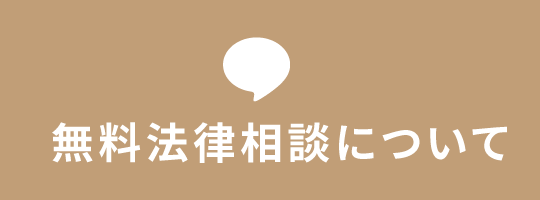遺留分侵害額請求をされた場合、請求者(遺留分権利者)からの主張に対応する必要があります。遺留分侵害額請求を受けたからといって、すぐに支払いに応じる必要はありません。
まずは冷静に対応し、請求内容を確認した上で適切に対処することが重要です。
以下では、遺留分侵害額請求をされた場合の具体的な対処法について解説します。
このページの目次
1. 遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、相続財産の分配において遺留分を侵害されたと考える相続人が、財産を多く受け取った相続人や受贈者に対して、その侵害額を請求する制度です。
- 遺留分は法律で保障された最低限の取り分です。
- 侵害額は金銭での支払いが原則です。
2. 請求を受けた場合の流れ
ステップ1: 請求内容の確認
まずは、請求内容が適切かどうかを確認します。
- 請求が遺留分に基づくものか
・遺留分侵害額請求の期限内(1年以内)に行われているか確認します。 - 請求金額が正しいか
・被相続人の遺産総額が適切に計算されているか。
・自分が受け取った財産が請求額の根拠として正確か。 - 財産評価の妥当性
・不動産や株式など、評価が複雑な財産について適切な金額が計算されているか確認します。

ステップ2: 対応方針を検討する
請求内容を確認した上で、以下のいずれかの方針を選びます。
1. 請求に応じる場合
- 請求金額が妥当であると判断した場合、支払い方法について話し合います。
- 一括払い、分割払いなどの方法を提案し、合意を目指します。
2. 一部に応じる場合
- 請求金額が一部不正確である場合、不正確な部分について異議を申し立てます。
- 支払いに応じる金額を提示し、調整を図ります。
3. 請求を拒否する場合
- 請求内容に根拠がない場合、異議を申し立てます。
- 法的な根拠に基づき、請求に応じない理由を説明します。

ステップ3: 請求者との交渉
請求内容に応じるか拒否するかにかかわらず、請求者と冷静に話し合いを行います。
- 感情的な対立を避ける: 話し合いが感情的になると解決が難しくなるため、冷静に対応します。
- 第三者の助言を求める: 弁護士を介入させることで、法的根拠に基づいた交渉が可能です。
- 金額の調整: 不動産やその他の財産の評価額について合意を得ることが重要です。

ステップ4: 調停や裁判への対応
交渉で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停や訴訟に進むことがあります。
調停
- 家庭裁判所で調停委員が仲介し、双方の意見を調整します。
- 調停調書が作成されれば、法的効力を持ちます。
裁判(訴訟)
- 調停が不成立の場合、裁判に進みます。
- 裁判では、遺留分侵害の有無や請求金額の適正性が審議されます。
3. 遺留分侵害額請求を受けた場合の注意点
(1) 請求に期限があることを確認
請求は、遺留分侵害を知った日から1年以内、または被相続人が死亡してから10年以内に行わなければ無効です。
(2) 財産評価の透明性を確保
不動産や株式などの評価が適切かどうか確認しましょう。必要に応じて、不動産鑑定士や税理士に相談することも重要です。
(3) 冷静かつ慎重に対応
感情的にならず、法的根拠に基づいて対処することが大切です。直接交渉が難しい場合は、弁護士を代理人に立てましょう。
(4) 他の相続人との連携
複数の相続人が関係する場合、他の相続人とも連携し、一貫した対応を取ることが重要です。
4. 弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求を受けた場合、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
- 請求の適正性を確認: 財産評価や請求額の根拠を法律的に精査します。
- 交渉の代理: 相続人間の感情的な対立を避け、冷静な交渉を進めます。
- 調停・裁判の対応: 裁判所での調停や訴訟において、適切な主張を行います。
- 手続きの負担軽減: 煩雑な書類作成や交渉を弁護士が代行します。
5. 当事務所のサポート内容
遺留分侵害額請求を受けた際、当事務所では次のようなサポートを提供します。
- 財産評価の確認: 被相続人の財産を調査し、適正な評価を行います。
- 請求内容の分析: 請求金額や根拠を法律的に精査します。
- 交渉代理: 相手方との交渉を代行し、最適な解決策を提案します。
- 調停・訴訟対応: 調停や裁判において、適切な主張を行います。
6. ご相談はお早めに
遺留分侵害額請求を受けた場合、迅速かつ適切に対応することが重要です。
「どのように対処すればよいかわからない」「請求額が正しいのか疑問がある」とお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
経験豊富な弁護士が、あなたの権利を守るために全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。