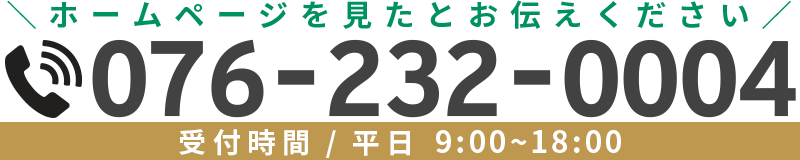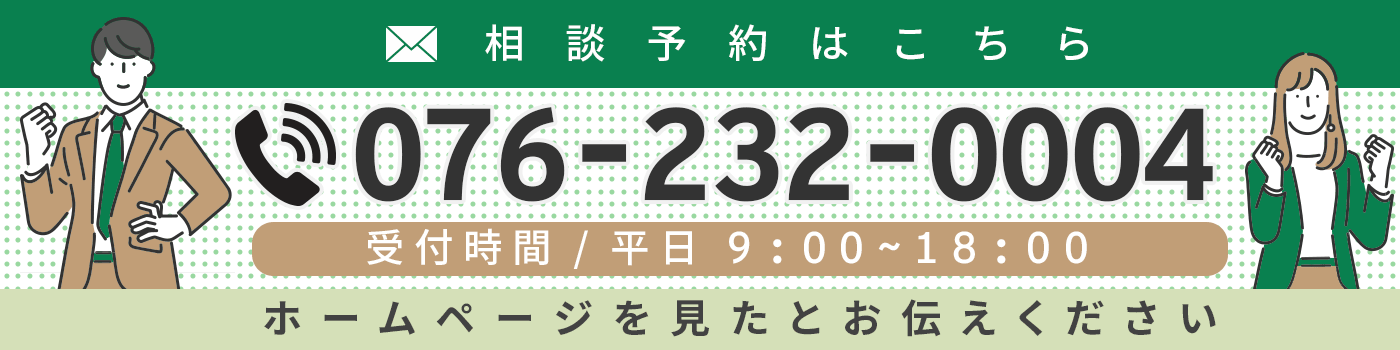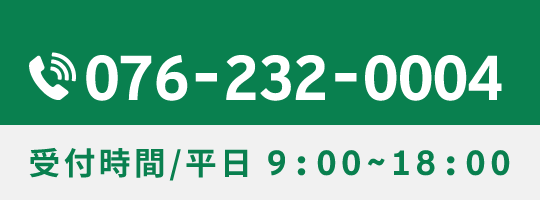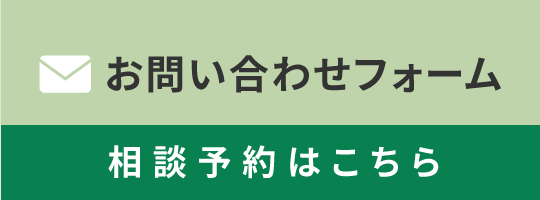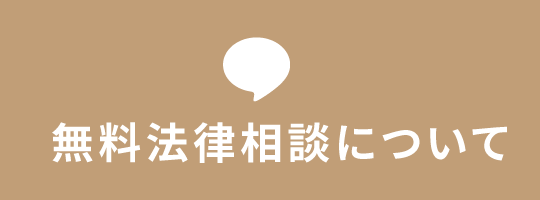遺留分侵害があった場合、適切な手続きを進めることで最低限の取り分を確保することができます。
ここでは、遺留分請求の具体的な流れを順を追って解説します。
このページの目次
1. 遺留分侵害を確認する
まず、遺留分が侵害されているかどうかを確認する必要があります。
ステップ1: 被相続人の財産を調査
調査内容:
- 被相続人が遺した財産(不動産、預貯金、有価証券など)
- 生前贈与された財産
確認資料:
- 遺言書(あれば内容を確認)
- 登記簿謄本、金融機関の残高証明書など

ステップ2: 遺留分を計算
遺留分は、被相続人の遺産総額に基づいて計算します。
遺留分 = 遺産総額 × 遺留分割合
遺留分割合の基準
- 配偶者や子どもが相続人の場合: 遺産の1/2
- 配偶者や直系尊属が相続人の場合: 遺産の1/3
2. 請求先を特定する
遺留分侵害額請求の相手は、財産を多く受け取った相続人や第三者です。
- 遺言によって特定の相続人が多くの財産を得た場合
- 生前贈与によって第三者が財産を受け取った場合
贈与が相続開始の10年以上前である場合、遺留分の対象外になることがあります。
3. 請求期限を確認する
遺留分侵害額請求には期限が設けられています。
以下のいずれか早い方を過ぎると請求権が消滅します。
- 遺留分侵害を知った日から1年以内
- 被相続人が死亡した日から10年以内
4. 遺留分請求の手続きを進める
ステップ1: 内容証明郵便で請求
まずは、遺留分を侵害した相手に対して内容証明郵便で請求を行います。
内容証明郵便に記載する内容
- 被相続人の名前と死亡日
- 遺留分の算定基準と請求額
- 支払いを求める期限
請求を内容証明郵便で行うことで、相手に請求した証拠を残すことができます。

ステップ2: 交渉・話し合い
内容証明郵便を送付した後、相手方と交渉を行います。多くの場合、以下の方法で解決します。
- 現金での支払い: 請求額を一括または分割で支払う。
- 財産の一部引き渡し: 不動産や動産などを引き渡すことで調整。

ステップ3: 調停や訴訟(交渉が不成立の場合)
話し合いで解決できない場合、家庭裁判所での調停や訴訟に進みます。
調停
- 家庭裁判所で調停委員が仲介し、双方の意見を調整します。
- 合意に至れば「調停調書」が作成され、法的効力を持ちます。
訴訟
- 調停が不成立の場合、訴訟に移行します。裁判所が遺留分侵害額を決定し、判決が下されます。
5. 調停・訴訟での必要書類
調停や訴訟では、以下の書類を準備する必要があります。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 遺産目録(財産の種類と評価額)
- 生前贈与の証拠資料(贈与契約書、振込履歴など)
- 遺言書(あれば)
6. 請求が認められた後の流れ
支払い・引き渡し
調停や訴訟で遺留分が認められた場合、請求額を現金や財産で受け取ります。具体的な支払い方法は以下のようになります。
- 現金: 相手が指定した口座に振り込む。
- 財産: 不動産や有価証券の名義を変更。
7. 遺留分請求の注意点
感情的な対立を避ける
遺留分請求は、相続人間で感情的な対立を招くことがあります。
弁護士を通じて請求することで、冷静で適切な対応が可能です。
財産評価を正確に行う
遺留分額を適切に請求するためには、不動産や株式などの財産評価が正確である必要があります。
不動産鑑定士や税理士の協力を得ると良いでしょう。
8. 当事務所が提供するサポート内容
遺留分請求に関する複雑な手続きや交渉を、当事務所が全面的にサポートいたします。
- 財産調査: 被相続人の財産を調査し、遺留分の適正額を算定します。
- 内容証明郵便の作成: 請求内容を法的に有効な形で作成し、送付を代行します。
- 交渉の代理: 感情的なトラブルを防ぎ、冷静で公平な交渉を行います。
- 調停・訴訟対応: 家庭裁判所での手続き全般を代理し、スムーズな解決を目指します。
9. まずはご相談ください
遺留分請求は、法律や税務の専門知識が必要な複雑な手続きです。
「遺留分が侵害された可能性がある」「どのように請求を進めればよいかわからない」とお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専門家があなたの権利を守り、円満な解決に向けて全力でサポートいたします。