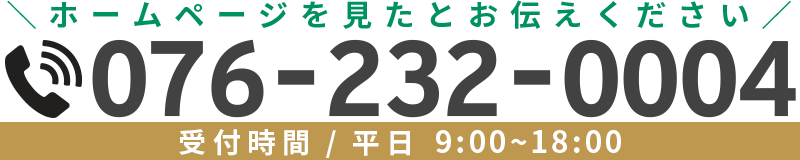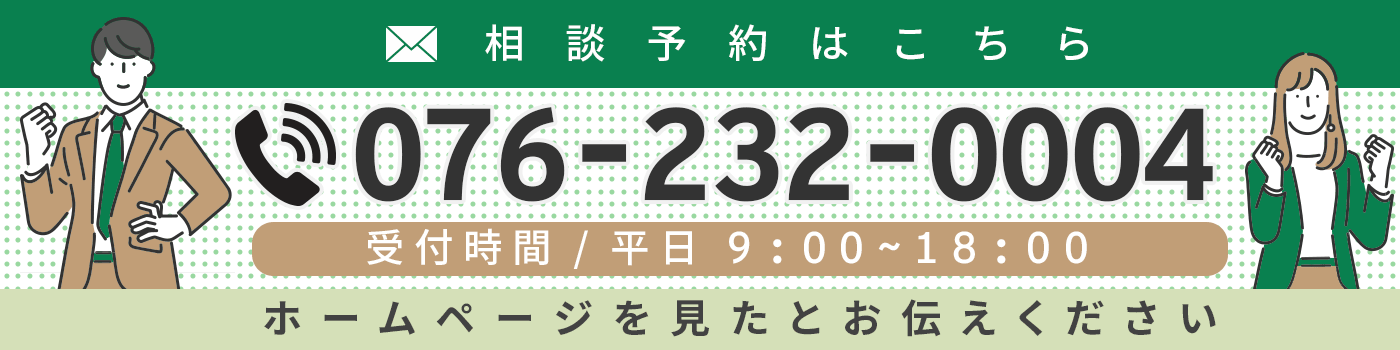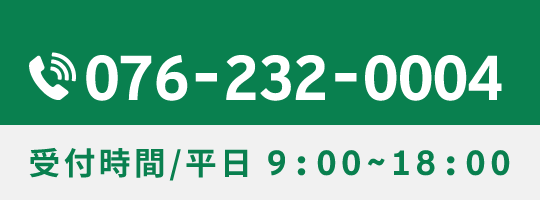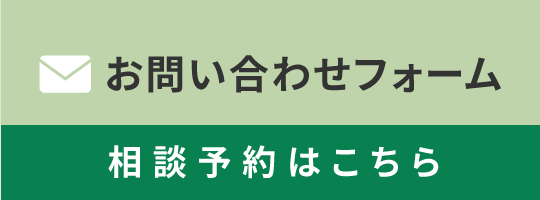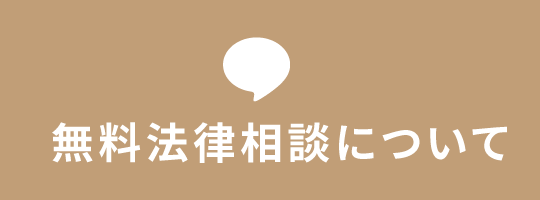遺留分は、法律で定められた相続人に最低限保証される取り分です。
遺留分を請求できる人(遺留分権利者)は、法律上の相続人のうち特定の範囲に限定されています。
以下では、遺留分を請求できる人について詳しく解説します。
このページの目次
1. 遺留分を請求できる相続人
遺留分を請求できるのは、以下の相続人です。
(1) 配偶者
被相続人の配偶者は、常に相続人となり、遺留分を請求する権利があります。
(2) 子ども(養子を含む)
被相続人の子どもは、法定相続人となり遺留分を請求できます。
- 代襲相続: 子どもがすでに死亡している場合、その子(孫)が遺留分を請求できます。
(3) 直系尊属(両親や祖父母)
被相続人に子どもがいない場合、直系尊属(両親や祖父母)が遺留分を請求できます。
- 両親が存命の場合、両親が相続人になります。
- 両親が亡くなっている場合、祖父母が相続人になります。
2. 遺留分を請求できない相続人
遺留分を請求できない相続人は以下の通りです。
(1) 兄弟姉妹
兄弟姉妹は相続人に該当する場合がありますが、遺留分の権利は認められていません。
- 代襲相続(兄弟姉妹の子ども)にも遺留分は適用されません。
(2) 相続放棄した人
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされるため、遺留分を請求する権利も失います。
3. 遺留分の割合
遺留分を請求できる範囲は、遺産総額に対して一定の割合で決まっています。
全体の遺留分割合
- 配偶者や子どもがいる場合: 遺産の1/2
- 配偶者や直系尊属(両親や祖父母)がいる場合: 遺産の1/3
個別の遺留分
全体の遺留分割合を法定相続分に基づいて各相続人に配分します。
例:
- 子どもが2人いる場合 → 各子どもの遺留分は「遺産の1/4(全体の1/2 ÷ 2)」
4. 遺留分請求の対象者
遺留分を請求できる人は、財産を多く受け取った以下の人たちに対して請求を行います。
(1) 遺言で財産を多く受け取った相続人
- 遺言により、特定の相続人に多くの財産が配分された場合、その相続人に遺留分侵害額を請求します。
(2) 生前贈与を受けた相続人や第三者
- 被相続人が生前に特定の相続人や第三者に多額の財産を贈与していた場合、その受贈者に請求を行います。
5. 遺留分を請求する際の注意点
(1) 時効に注意
遺留分請求には期限があります。以下のいずれか早い方を過ぎると請求権が消滅します。
- 遺留分侵害を知った日から1年以内
- 被相続人の死亡日から10年以内
(2) 財産調査が重要
適切な遺留分を請求するには、被相続人の財産(遺産総額)を正確に把握する必要があります。
- 不動産、預貯金、有価証券などの財産調査を十分に行いましょう。
(3) 感情的な対立を防ぐ
遺留分請求は家族間での対立を招きやすいため、弁護士を代理人に立てることで冷静に交渉を進めることができます。
6. 当事務所のサポート内容
遺留分請求をスムーズに進めるため、当事務所では以下のサポートを提供しています。
- 遺産調査: 被相続人の財産を調査し、遺留分の正確な額を算定します。
- 請求手続き代行: 内容証明郵便の作成や送付、請求交渉を代理で行います。
- 調停・訴訟対応: 家庭裁判所での調停や訴訟手続きにも対応可能です。
- トラブル解決: 相続人間の対立を調整し、円満な解決を目指します。
7. ご相談はお早めに
「遺留分が侵害されている可能性がある」「どのように請求すればよいかわからない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
法律の専門家があなたの権利を守るため、全力でサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。