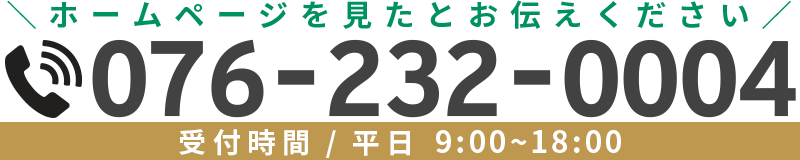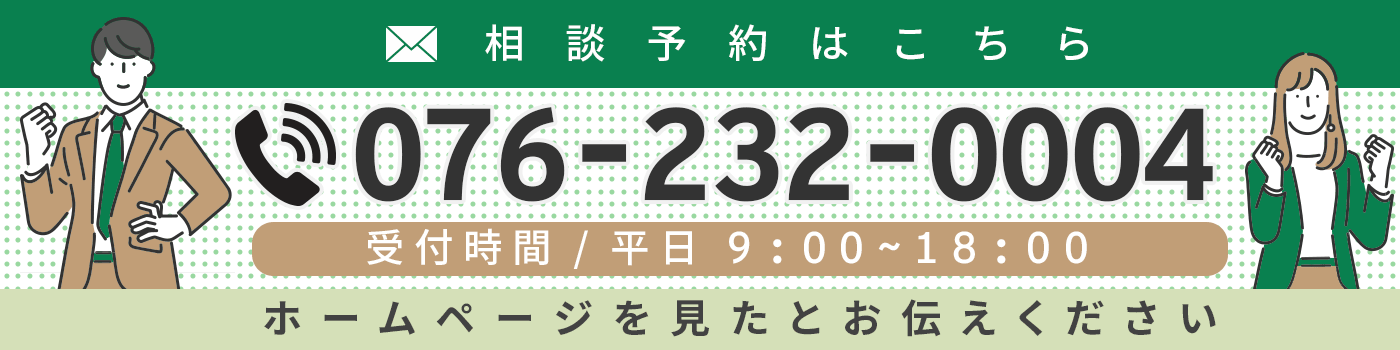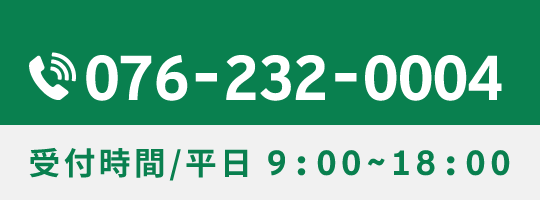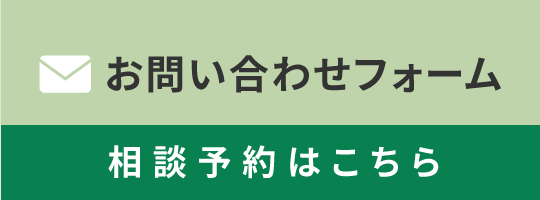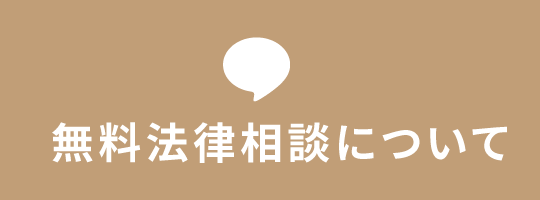遺産分割調停は、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所が間に入って話し合いを進める手続きです。
調停では、裁判所が選任した調停委員が中立的な立場で意見を調整し、円満な解決を目指します。
以下では、遺産分割調停の申立てから解決までの流れを詳しく解説します。
このページの目次
1. 遺産分割調停を申し立てる前の確認
調停が必要なケース
- 遺産分割協議が相続人全員の同意に至らない場合。
- 特定の相続人が協議に応じない場合。
- 分配方法や財産評価で意見が対立している場合。
調停の特徴
- 調停は、裁判所が関与するため公平な場が提供されます。
- 相続人が直接顔を合わせる必要はなく、個別に意見を述べることが可能です。
2. 調停の申立て先と管轄
申立て先
遺産分割調停は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
管轄の確認
裁判所の管轄地域は、裁判所の公式サイトや最寄りの裁判所で確認できます。
3. 調停申立ての流れ
ステップ1: 必要書類の準備
調停を申し立てるために、次の書類を準備します。
必要書類
- 調停申立書(家庭裁判所指定の用紙)
被相続人の氏名や住所、遺産の内容、申立人の意見を記載します。 - 相続関係説明図
被相続人と相続人の続柄を図示したもの。 - 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
相続関係を証明するために必要。 - 相続人全員の戸籍謄本
相続人であることを証明します。 - 遺産目録
不動産、預貯金、有価証券など、遺産の内容を一覧化したもの。 - 財産に関する証明書類
不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書など。
その他
家庭裁判所によって追加の書類を求められることがありますので、事前に確認が必要です。

ステップ2: 申立ての手続き
必要書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に申立書類を提出します。
費用
- 申立て手数料: 遺産の評価額に応じた収入印紙(数百円〜数千円)
- 郵便切手: 通知書の送付に必要(裁判所が指定する金額)

ステップ3: 調停期日の通知
裁判所から、調停期日の案内が申立人および相手方に送付されます。
- 期日の設定: 申立てから1〜2か月後が目安です。
- 調停の場: 調停は家庭裁判所内の会議室のような場所で行われます。

ステップ4: 調停の実施
調停期日には、申立人と相手方(他の相続人)が出席し、調停委員が仲介します。
調停の進め方
- 個別面談: 調停委員が申立人と相手方の意見を個別に聞き取ります。
- 調整: 調停委員が双方の意見を調整し、合意を目指します。
- 合意成立: 分配内容について全員が合意すれば、調停調書が作成されます。

ステップ5: 調停調書の作成
調停で合意が成立すると、「調停調書」が作成されます。
- 調停調書の効力: 調停調書は裁判所の判決と同じ法的効力を持ちます。
- 実務への利用: 名義変更手続きや相続税申告の際に使用します。
4. 調停が不成立の場合
調停でも話し合いがまとまらない場合、裁判所が遺産分割を決定する「審判」に移行します。
- 審判では、裁判官が法定相続分や相続人の事情を考慮して分割方法を決定します。
- 審判の結果に不服がある場合は、一定期間内に抗告することが可能です。
5. 遺産分割調停の注意点
1. 相続人全員の参加が必要
調停には、すべての相続人が参加しなければなりません。
相続人の特定を正確に行い、連絡を怠らないようにしましょう。
2. 感情的対立の回避
調停では感情的な対立が問題になることがあります。
調停委員が中立的に対応してくれますが、冷静に対応することが重要です。
3. 財産評価の透明性
不動産や株式など、評価が難しい財産については、専門家(不動産鑑定士や税理士)の意見を取り入れることが有効です。
6. 当事務所が提供するサポート内容
遺産分割調停の申立てや進行に不安がある場合、当事務所では次のようなサポートを提供しています。
- 申立書類の作成代行: 調停申立書や相続関係説明図、遺産目録の作成を代行します。
- 裁判所への同行: 調停期日に弁護士が同行し、申立人の意見を適切に主張します。
- 調停進行のアドバイス: 合意を目指すための戦略を立て、調停をスムーズに進めます。
- 不成立時の対応: 調停が不成立の場合、審判への対応も含めたサポートを行います。
7. ご相談はお早めに
遺産分割調停は、法的な知識や冷静な対応が求められるため、専門家のサポートが有効です。
「どのように進めればいいかわからない」「家族間での話し合いが難航している」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
専門家があなたの立場に立ち、スムーズな解決を目指してサポートいたします。